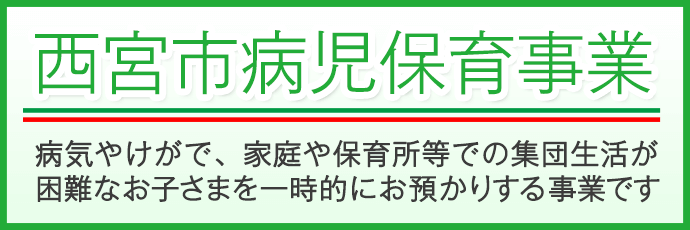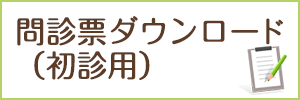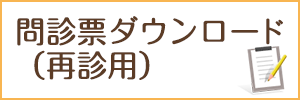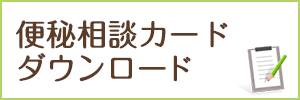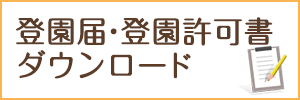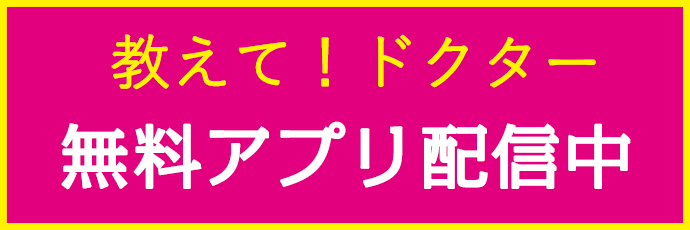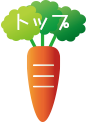医院紹介
- トップ
- 医院紹介
-
注意喚起と上手な通園方法
入所後はほとんどの子どもは色んな感染症に何度もかかります。
風邪かな?体調崩したかな?と思われたら、早い目に受診される事をお勧めします。我慢して高熱を出してしまうと何日もお休みをすることになったり、お母さんも仕事にいけません。軽症のうちに治療し、服薬しながら登園も可能な事も多いです。その際も保育園・幼稚園からの帰りに通院して管理していく事もできます。少しでも登園できる日を維持するためにクリニックを上手に利用してください。
-
6月は親子ともに疲れ気味(@_@;)?
保育園・幼稚園の送り迎えとお仕事、親子ともに緊張の毎日!
子どもを元気に登園させようと気遣ってきたお母さん。
この時期、お母さんにも疲れが出るころです。
お母さんも我慢されずに軽症のうちに受診治療されてください。
当医院では親御さんの薬も処方しますので遠慮なくご相談ください。 -
夏かぜとは…いつから登園できるかな?
夏かぜは多くが高温、高湿度を好むウイルスにより起こる感染症です。有効な治療薬はありません。症状を和らげる治療が中心です。予防は手洗いやうがいです。
≪ 登園登校について ≫
咽頭結膜熱(アデノウイルス感染)は、学校保健法で「主要症状が消失した後2日を経過するまで出席停止」と定められています。しかしヘルパンギーナと手足口病は出席停止になる感染症ではないので、高熱なく全身状態が安定していれば登園・登校は可能です。担当医と相談してください。 -
夏季旅行中の注意点
夏休みの帰省や旅行のため、長い日数の処方が必要な際は受診時に申し出てください。
他所への移動に備え、お薬手帳と母子手帳の携帯を忘れないようにしてください。 -
お盆明けの子どもの発熱や体調不良…?
お盆の長距離移動&帰省先での暮らしで疲れが出てしまったのでしょうか?
この様に普段の週末とは異なる生活環境や長距離移動が続くと、子どもの体調に影響してしまいます。子どもの様子や体調の変化に注意し、無理な登園や外出を控えて休養に務めるのが一番です。そしていつものリズムに戻してあげる事が大切です。親御さんも同様の事が言えます。子どものちょっとした不調に気付いてあげてください。気になる症状があれば、気軽に小児科受診してください。 -
インフルエンザ予防接種は…?
ウイルスに対する感染防御や発症阻止の効果は完全ではありませんが、感染しても発病を抑え、症状を軽くする効果があります。そのため1歳以上のお子さん、特に保育園・幼稚園・学校などの集団生活をしているお子さんには接種をお勧めします。できれば、ご両親も同時期に接種されることでお子さんを感染から守ってあげましょう!
-
抗インフルエンザ薬の予防投与…?
インフルエンザ予防は手洗い・うがい・マスク・加湿・予防注射ですが、発症を完全に防げるわけではありません。身近にインフルエンザ患者が発生した場合接触から36時間以内であれば、抗インフルエンザ薬の予防投与で7~8割の方がインフルエンザの発症を防げると言われています。ただし、投与期間内しか予防効果がないと言われています。また保健適応には色々な条件があります。多くの場合、公的医療保険が使えず自費診療の扱いとなります。
まずは、かかりつけ医に事情を説明し、相談してみましょう! -
おなかの風邪…?
おなかの風邪は「吐き下し」「嘔吐下痢症」「ウィルス性胃腸炎」など、様々な呼び方で呼ばれています。保育園・幼稚園などでは、集団感染が起こることが多いです。
治療の中心は小まめな水分補給、安静、整腸剤内服などの対処療法になります。
汚物・吐物の処理は、①早く処理、②乾燥させない、③消毒(塩素系)を守りましょう。
また、下痢の色が変な場合(白っぽい、黒っぽい、血便)は、速やかにかかりつけ医を受診し、診察と便の検査をしてもらう事も必要です。 -
お母さん、お父さんの風邪くすりも…
寒くなるにつれて、風邪症状の園児が増えてきます。お迎えの帰り道にお子さんの受診をされる際にはご要望があれば、親御さんの風邪くすりや胃腸薬、鎮痛解熱剤等の処方が可能です。遠慮せずにお気軽に申し出てください。
たとえ軽い風邪でも軽いうちに対処されるのが、早く治すコツです。
我慢しない!頑張りすぎない!お子さんと一緒に早く治してくださいね! -
予防接種の期限…?
予防接種には接種期間が決められています。期間を過ぎてしまうと自費扱いになるだけでなく、有害事象が起こった際の補償も大きく異なります。
- B型肝炎
- :1歳に至るまでの間
- BCG
- :1歳に至るまでの間
- 麻疹・風疹
- :12ヵ月から24ヵ月に至るまでの間
- 水痘
- :12ヵ月から36ヵ月に至るまでの間
- ヒブ
- :60ヵ月(5歳)に至るまで間
- 肺炎球菌
- :60ヵ月(5歳)に至るまで間
- 四種混合
- :90ヵ月(7歳6ヵ月)に至るまで間
- 日本脳炎
- :6ヵ月から90ヵ月(7歳6ヵ月)に至るまでの間
今一度母子手帳をご確認ください。わからない時はかかりつけ医に相談しましょう!
-
予防接種週間:3月1日(日)~7日(土)
4月からの入園・入学に備えて必要な予防接種をすませ、病気を未然に防ぎましょう!
今一度母子手帳をご確認ください。特に3歳までの水痘、年長さんのMR(麻疹・風疹)5歳までのヒブ・肺炎球菌ワクチン。
わからない時は「かかりつけ医」に遠慮なく相談しましょう! -
保育園児の感染対策
登園する朝には必ず検温して37.5℃以上の熱の有無をチェックしましょう!
保育中に発熱した患児は翌日も休んで自宅での療養を指示する保育所が増えてます。まる1日は発熱がないことを確認して登園してくださいとする対応の所が多いようです。まだ有効な治療薬も予防接種もないため、家庭での食事と十分な睡眠・休養で免疫力を維持することが大切です。
不安な時は登園前に「かかりつけ医」を受診して相談してください。 -
家庭での対応
登園を自粛するように要望する保育園も多くなってきました。
余儀なく仕事を休んで、自宅で子どもと過ごす時間が増えることと思われます。
親子ともにストレスが溜まりますが、子どもにとって、お母さんが笑ってくれているのが一番安心できることです。仕事・家事など心配なことも多々ありますが、笑顔を見せてください。
きっと子どもも笑顔になりますよ。
不安な時は「かかりつけ医」に遠慮なく相談してください。TEL:0798-35-1001 -
保育所での対応
6月いっぱいは通園児童の制限があるかもしれませんが、通園可能となったら下記の注意をご確認ください。
- 登園前に自宅での検温と健康チェック(咳・のどの痛み・鼻汁・頭痛・体のだるさ)をしてください。何か症状があるようでしたら、かかりつけ医にご相談ください。その際は、事前に電話で連絡してから受診するようにしてください。TEL:0798-35-1001
- 登園したら、保育園の感染対策に従って行動してください。
- ご家族や勤務先などで、新型コロナウイルス感染者または感染した恐れがある方が出た場合は、速やかに施設に連絡してください。
-
保育所完全再開後の留意点
まだまだ厳しい条件を出す保育園も多いですが、下記の留意点を意識して子どもさんを保育所に継続して登園できるようにしてあげてください。
- 登園前に自宅での検温と健康チェック
- 夕方のお迎え時に風邪気味だったり、少し元気がない様子があれば、遠慮せず夕診に立ち寄って診察を受けてください。早期治療と翌日の登園の判断を一緒に考えましょう!
-
夏季熱
登園前の検温で微熱に気付き、迷う事があります。
夏季熱は主に乳幼児がかかる病気で、夏の暑い時期に原因不明の37度台の熱が続く症状のことを言います。
体温調節が未熟な赤ちゃんにみられます。少し涼しくして水分を与えると軽快することが多いです。
それでも解熱せず辛そうなら感染症かもしれません。「かかりつけ医」を受診しましょう! -
インフルエンザワクチン
厚生労働省は今冬のインフルエンザ感染と新型コロナウイルス感染の同時流行を懸念して医療従事者、高齢者、基礎疾患のある患者に加え、小児「特に乳幼児~小学校低学年(2年生)」へのインフルエンザワクチン接種を強く推奨しています。集団保育の乳幼児はできるだけ10~11月中に2回接種を受けてください。子どもさんと同時に親の接種もできます。
-
インフルエンザワクチンと卵アレルギー
ワクチンは高度に精製され、その卵成分は極めて微量であり、通常は卵アレルギーがあってもほとんど問題となりません。
但し、重篤な卵アレルギーがある方は、接種を見合わせます。心配な方は予約時にかかりつけ医と相談してください。インフルエンザワクチンが接種できない場合の対応
- 発症(発熱)したら、診断後ただちに抗インフルエンザ薬を服用する。
- 感染者と濃厚接触した場合には、ただちに抗インフルエンザ薬を予防的に服用する。
(但し、保険診療でなく有料です。有効期間も限られています)
-
新型コロナ対策はインフルエンザにも有効!
個人の感染対策として身近になった、手洗い・うがい・手指消毒・咳エチケットは、インフルエンザの感染予防にも有効と言われています。
- こまめな手洗いと手指消毒
- 咳エチケットの徹底(マスクをする、マスクがない時は手や袖で口を覆う)
- 部屋の換気と加湿をする
- バランスのとれた食事を摂取し十分に睡眠をとって、体力・免疫力をつける
これらの基本的な感染症対策を、忘れずに心がけていきましょう。
-
年末年始の対応
軽症のうちにかかりつけ医を受診して軽快を目指してください!
急病の発生時は慌てないで下記の施設や電話相談などを利用してください。
受診が必要か判断に迷ったら(電話相談)- 1.24時間電話医療相談
- 健康医療相談ハローにしのみや(西宮市在住の方が対象)
【電話】0120-86-2438
【相談時間】24時間・年中無休 - 2.小児救急医療電話相談
- 阪神南圏域 小児救急医療電話相談(西宮市・尼崎市・芦屋市に在住の方が対象)
【電話】06-6436-9988
【相談時間】月曜~金曜:21時~深夜0時
土曜・日曜・祝日・年末年始(12月29日~1月3日):16時~深夜0時 - 兵庫県 こども医療電話相談(兵庫県に在住の方が対象)
【電話】#8000(市外局番が06、072以外のプッシュホン回線、携帯、公衆電話)
【電話】078-304-8899(市外局番が06、072、ダイヤル回線、IP電話等)
【相談時間】月曜~土曜:18時~翌朝8時
日曜・祝日・年末年始(12月29日~1月3日):8時~翌朝8時 - 阪神北広域 こども急病センター電話相談
(西宮市・伊丹市・宝塚市・川西市・猪名川町に在住の方が対象)
【電話】072-770-9981
【相談時間】毎日:深夜0時~翌朝6時30分
-
長引く鼻水・鼻づまりに注意!
冬季は軽い咳や水鼻でも、元気に登園してくる園児が増えます。
中耳炎は3歳までにほとんどの子どもがかかると言われています。鼻やのどのかぜに引き続きおこります。お子様が黄色い鼻水が出たり、耳を触っていたら中耳炎のサインです。
小児科受診時にはのど・鼻に続き、耳も診てもらいましょう!お鼻の処置も必要な事があります。
-
コロナ禍でも予防接種と定期健診は受けましょう!
・予防接種の接種間隔のルールが簡単になりました。
2020年10月から、注射生ワクチンの後に注射生ワクチンを接種するときに限り4週間(中27日)空ける以外の制限はなくなりました。なお、同じ種類のワクチンを複数回接種する時には、それぞれワクチンで決められた間隔を空ける必要があります。(参照:VPDを知って、こどもを守ろうの会)
かかりつけ医と相談して効率の良い接種計画を立ててもらいましょう。・乳児健診
本年度も4か月健診と10か月健診は医療機関での個別健診となっています。 -
予防接種の延期や接種忘れはありませんか?
乳児健診もお忘れなく!- B型肝炎・BCG
- 接種期間は1歳未満
- MR(麻疹・風疹)
- Ⅰ期の接種期間は1歳~2歳未満
Ⅱ期の接種期間は5歳~7歳未満(小学校就学前の1年間)
定期接種の場合、規定の期間内に予防接種を受けられなかった方でも、公費で受けられる場合があります。かかりつけ医やお住まいの市区町村にご相談ください。
・乳児健診
本年度も4か月健診と10か月健診は医療機関での個別健診となっています。 -
コロナ禍でこそ、かかりつけ医を持ちましょう!
「かかりつけ医」とは日常的な診療や健康管理をしてくれて、なんでも相談しやすい身近なお医者さんです。
コロナ禍の過度な受診控えは健康上のリスクにもつながります。発熱時や健康上の不安がある時、予防接種や健診を受けたい時など、適切な対応・相談を行います。 -
新型コロナ禍でのくらし
保育園・幼稚園・学校は感染対策を取りながらやっております。
感染予防の注意点を守れば、外出や子ども同士の遊びは可能です。
軽い症状でも早い目にかかりつけ医を受診し、治療を受けましょう!
予防接種や健診などの時期が決められたものは待たずに積極的に受けましょう!*新型コロナウイルス感染を疑ったら、まずすべきことは
- 周囲の感染状況を確認。
- 子どもさん状態の把握:発熱と乾いた咳を認める一方で、
鼻汁鼻閉などの上気道症状が比較的少ない。
一部の患者では嘔吐、腹痛やげりなどの消化器症状も認めるようです。 - 子どもの患者の多くは、家庭内での感染です。
家庭内での感染予防にも留意してください。
受診に関して迷うようであれば、まず「かかりつけ医」に連絡を取りましょう。
強く感染が疑われれば、西宮市保健所の新型コロナウイルス医療相談窓口:0798-26-2240に連絡を取ってください。 -
緊急事態宣言下の受診と健診・予防接種およびコロナ感染対策
- 受 診:
- 軽い症状でも早い目に受診し、治療を受けましょう!
予防接種や健診などの時期が決められたものは待たずに積極的に受けましょう! - 予防接種:
- 特に接種期間の短いロタウイルスワクチンは生後6週から接種できますが、ほかのワクチンとの同時接種を考えて、生後2か月からが最適です。
現在、日本脳炎とおたふくかぜワクチンの不足が起こっております。お問い合わせください! - 乳児健診:
- 乳児健診も受けるべき時期が決まっています。
-
- 4か月健診:生後4か月~6か月になる月中
- 10か月健診:生後10か月~11か月になる月中
- ※受診に関して迷うようであれば、まず「かかりつけ医」に連絡を取りましょう。
- コロナ感染対策:
- 子どものコロナ感染は家族内感染が多いため、親の感染防御とワクチン接種がポイントです。
もしコロナ感染が強く疑われれば、西宮市保健所の新型コロナウイルス医療相談窓口:0798-26-2240に連絡を取ってください。
-
感染症にかかった時の登園のめやす----主に夏季に関して
医師が意見書を記入する疾患:
アデノウイルス感染症・水ぼうそう・おたふくかぜ医師の診断を受け、保護者が登園届を記入する疾患:
溶連菌感染症・マイコプラズマ肺炎・RSウイルス感染症・ウイルス性胃腸炎・手足口病・リンゴ病・ヘルパンギーナ各疾患それぞれで登園のめやすがあります。かかりつけ医に指示を受けて登園の可否を決めてください。
-
夏の皮膚病
- 水いぼ:
- 伝染性軟属腫(でんせんせいなんぞくしゅ)といいます。放っておいても1~2年で治ることが多いですが、別の部位に広がったり、ほかの子どもにうつしてしまうこともあります。
当院では痛み軽減目的で処置前に麻酔テープを貼付後、ピンセットで摘除しています。 - とびひ:
- 伝染性膿痂疹(でんせんせいのうかしん)といいます。
水ぶくれができるタイプ(水疱性膿痂疹:すいほうせいのうかしん)と、かさぶたができるタイプ(痂皮性膿痂疹:かひせいのうかしん)の2つがあります。 - ■ 対処法:患部の清潔を保つことが大切です。石鹸をよく泡立ててやさしく患部を洗い、シャワーでしっかり洗い流すようにします。
ほかの人にうつるのを避けるため、プール(水泳やプール遊び)は治癒するまで控えます。
タオルや衣類からうつる可能性もあるため、家族や友達との共用は控えます。
症状が重い場合や、なかなかよくならない場合などには医療機関を受診しましょう。
抗菌薬の内服や外用薬による治療が行われます。かゆみが強い場合には、抗ヒスタミン薬などが用いられます。
※いずれも登園のめやすがあります。かかりつけ医に指示を受けて登園の可否を決めてください。
-
小児のコロナ対策
- 基本的な感染対策(3密回避、適切なマスク着用、手洗いなど)の徹底が重要です。
- 12歳以上の兄姉と同居家族のワクチン接種をして、予防に努める。
- 感染の可能性が考えられる場合は、市または県のコロナ相談センターに問い合わせる。
新型コロナウイルス感染症 電話相談窓口
電話:0798-26-2240(平日受付:9時~19時 土日祝受付:9時~17時)
(時間外で繋がらない場合は、西宮市役所代表電話:0798-35-3151)兵庫県:新型コロナ健康相談コールセンター
電話:078-362-9980(受付時間:24時間 土曜日・日曜日・祝日含む)
-
コロナ禍のインフルエンザワクチン
昨年はインフルエンザは流行しませんでした。これは国内で新型コロナウイルスが広がり始めたことで、手洗い・うがい・マスクといった対策を行ったためだと言われています。昨年流行しなかった分、免疫が下がって爆発的に増える可能性もあると言います。
新型コロナウイルス感染との同時流行も考えられます。症状からでは見分けにくい場合もあります。そのため、重症化しやすい高齢者や基礎疾患のある人および小児は積極的に接種すべきと考えます。
インフルエンザは例年12月頃から流行し、1月末~3月上旬にピークを迎えます。
10月からのインフルエンザワクチンを行う予防策が推奨されます。
インフルエンザワクチンは接種後2週間程度で抗体ができ、5ヵ月間程度効果があります。 -
コロナ禍、冬に流行する病気
新型コロナウイルス感染症は沈静化傾向にありますが、冬に流行する他の感染症にも注意が必要です。
インフルエンザウイルス、RSウイルス。感染性胃腸炎(ノロウイルス・ロタウイルスなど)いずれも予防は現在の感染対策をゆるめず続けることが大事です。
集団保育では、かかったかな?と思ったら、軽症のうちに早く受診しましょう! -
年末年始の対応
年末年始はかかりつけ医も休診の所が多いです。休日や夜間などの緊急時に受診できる施設や連絡先の情報を調べておきましょう!このホームページの「お役立ちリンク集」も参照ください。
また「教えてドクター」のアプリもお母さんの携帯に入れて活用ください。 -
嘔吐した時の対応ポイント → ちびちび・ごっくん
- 吐いた後、すぐには何も与えずに1~2時間ほど様子を見て大丈夫そうなら水分を少量ずつあげてください。
- スプーン1杯程度の少量から開始して、5~15分くらいあけて少しずつ増量してあげてください。
決して、(嘔いてなくても)すぐにたくさんの水分をあげないようにしてください。 - 水分は、塩分を含んだ飲料水のOS1や味噌汁の上澄みなどを少量ずつあげてください。
※市販のスポーツ飲料は塩分含有量が少ないため、嘔吐初期にはふさわしくありません。
※OS1などがない場合は、500mlのペットボトルの水に1g(小さじ4分の1杯程度)の塩を入れ、砂糖20g(大さじ2杯位)とレモンを数滴お好みでいれると飲みやすくカリウムの補給になります。 - 吐くのがおさまり、水分もある程度とれるようになれば、食事を開始してください。
消化吸収の良い、おかゆ、野菜スープ、煮込みうどん(短く刻む)等を少量ずつゆっくり食べさせてあげてください。
-
お子さんの投薬と同時に親御さんの投薬
新型コロナ感染第6波の影響でクリニック受診を見合わせておられる患者さんが多いようです。
お子さんの定期内薬や外用剤の処方のみも保護者の方とのお話の上、処方可能です。
またお子さんの受診に際して、同時に保護者の方の処方も可能です。遠慮なく申し出てください。 -
まん延防止等重点措置実施下の受診
新型コロナ感染の疑いがある時は「コロナ相談センター」にお問い合わせください。
西宮市新型コロナウイルス医療相談窓口(発熱等受診・相談センター)
TEL:0798-26-2240
平日:9~19時、土日祝日:9~17時感染の可能性がない場合はお問い合わせの上、受診の必要性をご相談ください。
受診が不安な方は親御さんだけで来院の上、お話を聞かせて頂き対応します。
定期処方や外用剤の処方も可能です。 -
春先は溶連菌が流行しやすい!
溶連菌感染はのどの痛みと発熱があるが、咳・鼻水の症状がないのが特徴です。
のどの迅速診断で検査ができます。長く抗生剤を服用して合併症を予防します。
抗生剤を服用して解熱すれば、登園可能です。
予防は他の感染症にも共通する「マスク・手洗い・うがい」です。 -
入園当初の病気対策
通い始めの4月から5月はいろんな感染症にかかります。
- 登園前に自宅での検温と健康チェック。気になったら、時間が許せば登園前に受診しましょう。
- 夕方のお迎え時に風邪気味だったり、元気がない場合は迷わず夕診に立ち寄って診察を受けてください。早期治療と翌日の登園の判断を一緒に考えましょう!
-
感染性胃腸炎に注意!
現在、市内で一番患者の多い疾患です。多くはウイルス性で感染力は強いです。
嘔吐や下痢が見られたら、早く小児科を受診してください。水分の小まめな摂取が肝要です。
便の迅速診断でわかるウイルスもあります。
アルコール消毒では効果が弱く、次亜塩素酸ナトリウム(ハイタ―)による消毒が有効です。 -
病児保育!
お子様の急な病気やけがで、保育所等での集団保育を利用することができず、保護者の就労等の事情で家庭での保育が困難な場合に、お子様を一時的にお預かりする事業です。
病児保育ネット予約サービス「あずかるこちゃん」への登録が必要です。
【分かりにくい場合のお問合せ先】保育幼稚園支援課:0798-35-3044 -
新型コロナ感染の患児
第7波では小児の感染者が多いようです。この時期は高熱が出る他の感染症も多いです。
症状だけでは区別困難です。疑わしい時は受診するか新型コロナウイルス感染症医療相談窓口(☎0798-26-2240)に問い合わせください。
症状のある感染者は自宅療養期間として「発症の翌日から10日間かつ症状軽快後72時間経過するまで」となっております。同居の方に関しては保健所からの指示に従ってください。 -
乳幼児の便秘
集団生活に入るとお腹の調子も不安定になります。便秘はみんなが経験する症状です。
《家庭でできる便秘の対処法》
- 「の」の字マッサージ
- 肛門刺激や綿棒浣腸
- 足を動かす運動
- 白湯やうすい果汁を飲ませる
うんちは健康のバロメーターです。かたい・ゆるい・匂いがおかしい?いつもと違うな?と思ったら、おむつごとかかりつけ医に見せてください。
-
2022-2023のインフルエンザワクチン
2022年4月中旬以降、南半球のオーストラリアで6月をピークに5~9歳が最多。次いで5歳未満、10~19歳に感染者が多いと報告されています。
9月末の時点で沖縄県50名、東京近隣の県で数名ずつ感染の報告が出ています。日本での流行が懸念されています。
そのため日本ワクチン学会はワクチン接種を強く推奨しています。
また疑わしい症状がある時は、コロナとインフルエンザの鑑別のためにも迅速診断を受けましょう! -
この冬の感染対策
この冬は、新型コロナウイルス感染と季節性インフルエンザ感染の同時流行が懸念されています。
疑わしい症状がある時は、コロナとインフルエンザの鑑別のためにも迅速診断を受けましょう!
インフルエンザ感染には治療薬がありますが、小児のコロナ感染の治療薬はありません。
一定期間自宅での療養と対症療法が主体です。他の冬季の感染症(RSウイルス・ヒトメタニューモウイルス・腸管感染:ノロウイルス・アデノウイルス・ロタウイルス)も含め、早期の診断とその対応に留意ください。 -
新型コロナワクチン接種に対する考え方
日本小児科学会では2022年8月の5~17歳の子どもへのワクチン接種推奨の発表に続き、2022年11月2日には「生後6ヵ月~5歳未満の子どもへの新型コロナワクチン接種を推奨する」と表明しました。
オミクロン株流行期におけるワクチンの発症予防効果は生後6ヵ月~2歳未満では75.6%、2~4歳児では71.8%とされており、重症化予防はさらに上回ることが期待されています。外来でご相談ください。 -
冬の胃腸風邪(吐き下し)に対する対処法
多くはウイルス性胃腸炎ですので、治療薬はありません。対処療法になります。
特に嘔吐症状がきつい時は吐き気が治まるのを待って、少量の水分をこまめに摂ることです。
家庭での感染対策としては- 手洗い・嘔吐物糞便の処理
- 消毒:消毒用アルコールではなく、次亜塩素酸ナトリウム(塩素系漂白剤)が有効です。
-
公費で受けられる予防接種、対象者の年齢を確認!
定められた年齢期間に接種できない場合、自費扱いになります。母子手帳をご確認ください。
不明な点があれば、母子手帳をご持参の上、相談にお越しください。
特に接種漏れがみられる予防接種を列記します。ご確認ください。- 麻疹・風疹(MR)の第2期:
- 5歳以上7歳未満のうち、就学前1年間(年長さん)
- 日本脳炎の第2期:
- 9歳以上13歳未満
- 水ぼうそう:
- 生後12か月から36か月に至るまで
- BCGおよびB型肝炎:
- 生後1歳に至るまで
-
入園前の心構え
具体的に実践したいこと3つ
- 1.保育園の生活リズムをを知って予習
- 保育園ではおおよその生活リズムが決まっています。散歩、お昼寝、食事など、何日間か保育園と同じリズムで生活してみる。
- 2.登園経路を確認
- 朝の経路を、予定している時間に予定している方法で移動してみましょう。晴れの日だけでなく雨の日も想定しておくとさらにいいです。
- 3.少しの時間、子どもを預けてみよう
- 市区町村の提供するファミリーサポートセンターや一時保育を利用したり、心配ならおじいちゃんおばあちゃんにでも構いません。
-
給付金・助成金ガイド
国や地方自治体などから支給されるお金のこと。西宮市のホームページをこまめにチェックして利用していきましょう!
- 児童手当、児童扶養手当、幼児教育・保育の補助、乳幼児・子どもの医療費助成、こどもエコすまい支援事業 ⇒ 市区町村窓口
- 家族手当、健康保険料・厚生年金保険料の免除、育児休業給付金 ⇒ 勤務先
- 「130万円の壁」の穴埋め給付 ⇒ 市区町村窓口
- 育児用品補助、給食費の支援、こども教育・生活支援事業、予防接種費用助成 ⇒ 市区町村窓口
ここに紹介しているのは子育て支援の一部です。市区町村によって制度の有無は異なります。各窓口に問い合わせてみましょう!
-
入園当初の親子対策
入園・入学後1か月くらいで疲れやストレスから体調を崩す子どもさんが多くなります。
対応としては軽症のうちに受診して治しましょう!
親御さんも緊張がほぐれて、子どもさんと同じような風邪をひいたり、お腹の調子が狂ったりします。
当院では子どもさんと同時に親御さんの診察・処方もしています。遠慮なくお申し出ください。
子どもさんの通園と親御さんの仕事の継続に役立てればと心から願っています。 -
病児保育
病児保育を依頼する場合は、事前に病児保育施設へ連絡をとって利用できるか確認したうえで、病児保育依頼書を希望してください。依頼用紙がなければ、当院にも予備があります。
申請費用は自費(1,000円)です。 -
かくれ脱水
軽い脱水(体重の2%以下)では「のどの渇き」以外の症状がないため、気付かれ難いです。
赤ちゃんや言葉が話せない幼児は「のどが渇いた」と教えてくれません。
ですので、周囲にいる大人がこまめに水分補給を促してあげる必要があります。
保育園のお迎え時にお子さんの様子をよく見てあげてください。 -
夏のスキンケア
- むしさされ:
- 皮膚の露出を抑える。虫よけスプレーを使う。かゆみ止め軟膏やステロイド外用剤を準備しましょう。
- 日焼け:
- 日焼け止めは海や山では「SPF」20~40、「PA」++~+++を目安にしましょう!
使用後はきちんと洗い落として保湿剤を塗っておきましょう! - あせも:
- 予防はシャワーや入浴、着替えなどを適宜しましょう!
軽症であれば、清拭後に「あせもローション」の塗布が有用です。
-
子どもの夏バテ
子どもは大人よりも体の水分割合が大きいため、夏バテになりやすいです。
小さい子どもは自分で夏バテの症状に気づけないことも多いため、保護者が子どもの様子を確認することが大切です。
【症状】だるさ・食欲不振・下痢など胃腸の不良・やる気がない・不眠・手足の冷えなど【家庭でできる、夏バテ回復のための対処方法】
- エアコンの温度は25~27℃に設定。
- 冷たいものは控えめに、電解質が入った水分をぬるめにして飲ませましょう。
- 栄養と食べやすさを考えた食事を作ってあげましょう。また普段よりも少しだけ塩分を多めに!
- 体のリズムを朝型に修正しましょう。
-
秋から冬の感染症
流行状態にある新型コロナ感染症・季節性インフルエンザは高熱が主な症状です。
秋にはほっぺが赤くなるリンゴ病、頑固な咳のRSウイルス感染・マイコプラズマ感染、嘔吐・下痢の感染性胃腸炎も見られるようになります。
疑わしい時は速やかに受診して診断・治療を受けましょう! -
3歳児検診
身体計測、歯科検診、視覚検査、聴覚検査も行われます。必ず受けましょう!
保育園・幼稚園には担当園医がいます。通園の際には保育士さんに気になることを伝えましょう。 -
感染予防のためのホームケア
- 手洗い
- 部屋の加湿とこまめな水分摂取
- 適度に換気や空気清浄機の設置
- バランスのとれた食事
- 十分な睡眠
※様子がおかしい場合は早い目にかかりつけ医へ。
-
休み明けの子どもが不安定なときの対処法
休み明けに不安定になる子は多くいます。下記の対応を参考にしてください。
- 病気の可能性もあるので、まずは優しく気持ちを聞いてみましょう。
- 子どもの気持ちを否定せず「1日だけ頑張ってみよう!」と伝えてみてください。
- 不安定になりやすい子は休み中も園や学校に行くときのように早起きさせましょう。
- 悩まないで、保育士さんや担任の先生に状況を伝えましょう。
- 怒らずに子どもの姿を受け止めてあげてください。
※様子がおかしい場合は早目にかかりつけ医へ受診させてください。
-
インフルエンザの診断と治療
高熱が出たら、インフルエンザ感染が考えられます。慌てずに様子を見ながら、発熱後24時間を目途に迅速検査を受けるようにしてください。ただし検査陰性でも患児の症状や周囲の状況で診断することもあります。
抗ウイルス薬も、発熱後1日ほど経過してからの服用が効果的です。【迅速診断(鼻腔)検査】
発症からの時間 感度
- ~12時間:
- 35.0%
- 12~24時間:
- 66.0%
- 24~48時間:
- 92.0%(発熱後1日位してから)
- 48時間~:
- 59.0%
-
入園前にしておくこと
入園前に準備するもの
- 通園カバン
- 着替え一式
- おむつ・おしりふき
- 食事用エプロン・スタイ
- マグ・コップ
- お昼寝用布団セット(保育園によって様々)
- 靴・靴下
- 汚れもの袋
- 帽子 すべてに名前記入が必要です!
入園前にやっておくと良いこと
- 保育園生活の予行練習
- 子どもに保育園のことを伝えておく
まとめ
保育園によって、必要なものや方針はさまざまですが、上記に挙げた必需品などは比較的どの園でも必要になってきます。
分からないことや確認しておきたいことがあれば、気軽に保育園へ電話したり直接行ってみて保育士さんに聞いてみてください♪ -
子育てママの体調管理
子どもを優先させて自分のことは疎かにしてしまいがちですが、自身の健康管理を行うことは家族全体にとって大変大事なことです。以下のポイントを参考にしてください。
子どもを預けて、お仕事されるママの心と体の健康管理
- 1日に1回、僅かでも自分のための時間をつくる。
- 自律神経を安定させる生活習慣を保つ。
- 子どもと一緒に自身のケアも心がける。
-
連休明けの対応
子どもたちは少しずつ緊張が解け、新しい生活に慣れようと一生懸命に頑張っています。
連休明けは登園を渋ったり、登園しても泣いていて一斉活動に参加できない子もいます。
親御さんからお子さんにしてあげてほしいことを列記しました。- 長期のお休みで生活リズムが崩れてしまったかもしれません。
眠い時に眠れる環境を用意したり、いつもより多めにスキンシップをとりましょう。 - 気分転換できるような工夫も大切です。
お子さんに寄り添い、気持ちを受け止めてあげてください。 - 些細な体調の変化がないか気をつけて見ていきましょう。
自宅での様子や体調の変化などがあれば、登園時に保育士さんにお伝えください。
身体的に気になることがあれば、かかりつけ医に相談しましょう。
- 長期のお休みで生活リズムが崩れてしまったかもしれません。
-
保育園で必要な登園届と登園許可証の違い
保育園で感染症に罹患された場合は、感染拡大を防ぐため保護者に登園届、もしくは登園許可証を記入してもらう事になります。
登園届と登園許可証。似ているようで全く違うものですが、実は覚えてほしい部分は1つだけ。- 登園届:
- 受診後保護者が記入する
- 登園許可証:
- 受診して医者が記入する
登園届の方が比較的感染力が小さく完治までの期間も早いもの。登園許可証は感染力が高いものが多いです。
用紙は保育園に備えてある場合が多いですが、当院でも用意しております。
こちらよりダウンロードしてご利用ください。 -
夏本番前にやっておきたいお掃除とお洗濯
- お掃除編
- ①フローリング・カーペットは掃除機+拭き掃除
➁お風呂のカビ(床・壁・天井・風呂ぶた)
③汚れた網戸・べランダ
④キッチンの油汚れ - お洗濯編
- ①布団・枕・カバー類
➁キッチン床マット
③カーテン・洗えるカーペット
※乳幼児の衣類は酵素系漂白剤を使って「こまめ洗い」がポイント。
しっかり2回すすぎしましょう!
-
夏休み・お盆休みの過ごし方
お盆期間中も開いている保育園は多くありますが、8月は多くの家庭が長中期の休みを取る時期です。
長期休暇中は普段と異なる生活が続くので、生活リズムが崩れる可能性も高まります。
普段と同じように『早寝早起き』する、『1日3食を食べる』など生活リズムが崩れないように心がけましょう。【夏の健康管理】
夏は気温と湿度が高い日が多く、疲れやすく体調を崩しやすい時期でもあります。
屋外で遊ぶ際には、適度に休憩を入れることや小まめな水分補給が肝要です。
長時間連続して遊ばないようにしましょう。 -
9月を健康的に過ごせるようにしていきましょう。
9月は、季節の変化による日照時間や気温の変化などにより、体調を崩しやすい時期です。長期休暇明けの子どもは、生活リズムの変化から、体調を崩したり、疲れを感じやすくなりがちです。『朝ごはんはしっかり食べているか』『しっかりと睡眠はできているか』『排便はできているか』などを、改めて確認してあげてください。
- 朝夜は涼しく日中は暖かい、という寒暖差がある時期です。気温の変化に対応ができるように、カーディガンや薄い上着などがあると便利です。
- 子どもが風邪をひいている時、微熱(37.5℃以下)で食欲もあればお風呂に入れても良いと言われています。
また、熱いお風呂は体力を消耗しますので、ぬるめの温度に設定しておきましょう。
お風呂で身体を清潔にし、気分をリフレッシュさせ、早く元気になりましょう。 - お家でできる夏バテ改善法
普段から軽い運動をし、お風呂にゆっくり浸かることで、汗をかく習慣を付けましょう。
また、夏野菜は体を冷やしてくれるので、しっかり摂りましょう。
味噌汁も、夏の疲れた胃腸にはぴったりです。
-
ファミリーでできる腸活
腸内環境は3歳までに決まるといわれているため、3歳までの生活や食事が重要です。
腸内細菌を整えるためには善玉菌(乳酸菌やビフィズス菌)を増やすことが大切です。
善玉菌はヨーグルトや納豆などの発酵食品に多く含まれます。
また食物繊維やオリゴ糖はその善玉菌の活動を活発にします。
腸内環境をよくすることは便秘の改善だけでなく、腸管免疫のアップにつながります。
日頃から、うんちの観察やうんちの話(排便回数だけでなく、色・形・ニオイなど)をしましょう。お母さんだけでなく、家族みんなで腸活に取り組み、腸内環境を整えることがポイントです。
-
冬に向けての乳幼児のお肌のお手入れ
寒くなると皮脂腺や汗腺の機能が不活発になり、肌は乾燥しやすくなります。
スキンケアの基本は洗浄と保湿です。- 洗浄はしわを伸ばして、たっぷり泡を付けて流し洗いしましょう。その後は押し拭きがいいです。
- 保湿は皮膚が温かく水分がある間にしっかりとしてあげましょう!
- モイスチャライザー:
- ヘパリン類似物質製剤、尿素製剤
- エモリエント:
- ワセリン製剤、ユベラ軟膏
モイスチャライザーは皮膚の保護効果に加えて保湿効果があるので、全身塗布に適しています。
エモリエントは皮膚の保護効果が優れているため、外界からの刺激が多い口回りや顔に使いましょう。
スキンケアをしっかりすることは肌が丈夫になるだけでなく、感染予防につながります! -
急な発熱でお迎えに行った後の対応
お迎えの時には保母さんから状況や状態を聞いて下さい。その場でお子さんの変わった様子はどうか観察して下さい。
時間が間に合えば、帰り時にかかりつけ医に診てもらいましょう。高熱時の自宅対応
- クーリング(頸部・腋下・鼠径部)、ぬるま湯での体幹の清拭、肌着の交換
- 水分補給:少量の水分をこまめに与える。(電解質飲料OS-1などをスプーン・スポイトで)
- それでも高熱が続き、辛そうであれば解熱剤の使用か?
状況により、救急診療所を受診を考えましょう。
- 前夜の高熱は翌日の登園の判断に参考になります。
言い換えると前日の高熱があれば、翌朝解熱していても自宅で療養し、かかりつけ医を受診しましょう。 - 親御さんが欠勤できない時には「病児保育」に頼る方法もあります。
-
ホームケアの基本
- 規則正しい生活を送る。たっぷり睡眠をとる。
- 栄養のバランスいい3食をとる。
- 手洗い・うがいの徹底。
- 部屋では適度な加温・加湿そして時々換気。
-
お口の育て方
顎は0歳~6歳に急激に発達します。口腔育成は虫歯や歯周病予防だけでなく、正しいお口の機能を身につけることで歯並びがきれいになり、将来健康にいきていくことにつながります。
歯並びが悪くなる悪い習慣に気を付けるポイントを列記します。- 口呼吸 : 顎の成長を妨げるだけでなく、細菌が増殖し歯肉炎の原因になります。
- 舌癖 : 普段何もしていない時に、舌が歯に触れている場合を指します。
- 嚥下 : 飲み込む時に舌を出したり、口回りに力の入る飲み込み方をすると歯並びが崩れます。
- 悪い姿勢: 猫背や食事の時に足がついていない姿勢は要注意です。
8歳を過ぎると顎の成長がゆっくりになるため、歯並びや根本的な原因の改善に時間がかかってしまいます。0歳からお口育てを習慣にしましょう!
-
年度末のお子さんへの対応
この1年間子どもたちの成長を温かく見守っていただき、ありがとうございました。
園の年度末に保護者と自宅で過ごす際には、園で覚えた簡単な遊びや過ごし方を一緒にしたり、子どもたちが出来るようになったことを思い返しながら、たくましく成長した様子を共有しましょう!また担当保育士さんからも子どもの楽しいエピソードも聞いてみましょう。
保護者の皆さまに感謝しつつ、子どもたちのさらなる成長を願っています。 -
入園当初の親の心配・不安解消法
- 園生活に慣れるのは、最初の学期いっぱいの時間がかかる
↓
時間をかけて徐々に慣れていく気持ちで過ごしましょう。 - 幼稚園の出来事を聞くのはほどほどに
↓
子どもにとって過去のことを話すのは簡単ではありません。 - 園服・園帽は初めは苦手な場合があります。
↓
園服の感触や帽子を嫌がる幼児は少なくありません。 - 友達づくりは、むずかしい
↓
集団生活の中で自分のことで精一杯で、まだ会話のやり取りも上手ではないです。 - 園とのコミニュ二ケーションを密に取りましょう。
↓
どうしても知りたい場合には先生に直接聞くのが確実です。
★ 一番の不安解消法は、慣れることを焦らず、頑張ってる子どもを温かく見守ってあげることです。★
- 園生活に慣れるのは、最初の学期いっぱいの時間がかかる
-
5月からの園児への対応
慣らし保育も終わったころにゴールデンウィークの連休があります。
連休明けは、気持ちが不安定になる子もいると思いますが、4月に築いた土台があるので、少しずつ生活リズムを取り戻し、のびのびと過ごせるようになるでしょう。5月の自宅でのポイント
- 生活リズム、生活習慣の安定化を意識しましょう!
- のびのびと過ごす時間を確保しましょう!
- 子どもの『好き』を見つけて、一緒に楽しみましょう!
-
若いお母さんのチャットGTP
チャットGPTは日に日に賢くなっていくAIのお陰で、頼りになる存在になっています。
育児に関する情報や相談にも対応してくれます。悩み多きお母さんの心の支えにもなっています。
医療関係のアプリでは「母子手帳アプリ 母子モ」「教えて!ドクター」が気軽に役立ちます。
今やAIは「自分の時間」と「心の余裕」を取り戻すパートナーになってくれます。 -
夏のスキンケア
たくさんの汗をかく子どもたちは、夏にも多くのスキントラブルをひきおこします。
常に皮膚の健康を保つように、正しいスキンケアをこころがけましょう。- 汗を沢山かいたり、下痢でおしりが汚れた時などは低刺激のスキンケアシートや蒸しタオルで小まめに拭いてあげましょう。ただし押さえるようにし、こすってはいけません!
できれば、シャワー浴をしましょう。石鹸やボディソープの使用は1日1回とし、皮脂をおとし過ぎないようにしましょう! - 清拭・入浴後はできるだけ早く、お顔から足先までまんべんなくたっぷり保湿しましょう。
保湿剤は塗りやすい乳液・ローション・泡タイプがお勧めです。 - 皮膚炎をおこしている場合には、十分に保湿した皮膚の上から処方された軟膏を塗りましょう。
- 寝るときは室温を下げ過ぎないように配慮し、薄着で熱がこもらない様に注意しましょう!
- 汗を沢山かいたり、下痢でおしりが汚れた時などは低刺激のスキンケアシートや蒸しタオルで小まめに拭いてあげましょう。ただし押さえるようにし、こすってはいけません!
外観・院内風景

入口
受付

待合
診察室

処置室
第二診察室

キッズスペース
化粧室